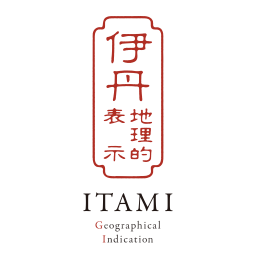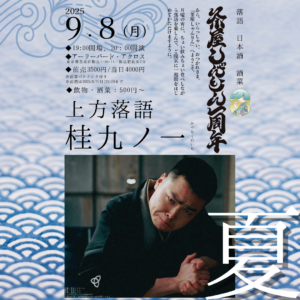日本酒地理的表示「GI喜多方」が指定されました。
GI喜多方
日本酒の地理的表示(GI認証)の19例目として、「喜多方」が、令和6年12月20日に指定されました。
酒類の特性について
喜多方の純米酒は、柔らかな丸みと芳醇な旨味の酒質で、リンゴやバナナといったフルーティな香りがあります。
爽やかな甘みを感じつつも軽快でキレの良い後味なので、東北地方で有数の生産量を誇る、喜多方のアスパラガスが持つ甘みを引き立てます。また、この地方で収穫されるそばの実等を使った山都そばをはじめとしたそば料理など、素材を生かしたシンプルな風味の料理と相性が良い酒質です。
気候風土
喜多方(福島県喜多方市及び隣接する同県耶麻郡西会津町)は、福島県の西部に広がる会津盆地の北部に位置し、北に飯豊連峰、西に越後山脈、東に磐梯山の頂を望む雄国山麓と、三方を雄大な山並みで囲まれた地域です。
これらの山々には2.5mを超える豪雪がつもり、雪解け水は地層へと染み渡り、阿賀川とその支流など多様な河川や湧水地を形成しています。これら河川の運搬によって地層は沖積層が形成されたことで、表面は農耕に適した堆積土でその下は砂礫層となっており、一方、この地層を通った豊富な伏流水は非常に軟質で、この地域の柔らかな丸みと芳醇な旨味を有する酒質に欠かせないものです。
この地域一帯は盆地特有の気候で、7~9月の昼夜の気温差が10度近くになり、稲の出穂時期であるこの時期に昼夜の寒暖差が生じることで米粒内にデンプンがしっかりとためられ、甘みのある米が育ちやすく、豊富な水と相まって古くから良質な米作りが行われてきました。このような環境から、この地域の酒造好適米である五百万石、飯米のコシヒカリ等の栽培が盛んで、これらの柔らかく甘みのある米が、この地域の酒質の特徴を支えています。
さらに、冬季の平均気温がマイナスであるなど酒造りに適した冬季の厳しい寒さと相まって、柔らかな丸みと芳醇な旨味を有しつつ後味の良い酒質となっています。

人的要因
喜多方の酒造りは、古くは寛永8年(1631年)頃の記録があり、小田付村・小荒井地区(現在の福島県喜多方市)を中心とした専業商人や半商半農の地主・豪商等や、近隣の宿場町であった野沢宿(現在の福島県耶麻郡西会津町)において、江戸時代の末期から明治時代(1800年代中頃から後半)にかけて盛んに行われていました。
この地域は海から遠く離れた山国で、米を輸送するための陸路と水路が脆弱であったため、余剰米の活用策として古くから酒造りが行われていました。近隣からの状態(鮮度)のよい米を使った酒造りがこの一帯で行われたことで、米の旨味や甘みが感じられる酒が造られてきたと推察されます。
この地域の酒蔵は、城下町(現在の福島県会津若松市)の酒蔵と異なり、会津藩からの庇護を受けることが難しかった中で、酒造りを生業として生き抜くために、酒蔵同士が力を合わせ、試行錯誤してきました。中でも、油商を営んでいた商家の冠木家が、明治に入り酒造業を営むようになってから、5代目当主である冠木房八が醸造技術の改良のため、寝食を忘れて研究に打ちこみ、その技術を地域の酒造業者たちに惜しみなく伝え、指導したとされており、喜多方地区の酒造業を営む当主のほとんどがこの5代目房八の醸造技術を学んだといわれています。
また野沢宿では、酒屋「石川屋(栄川)」の石川市十郎(栄四郎)が、酒造業を営みつつ農業技術の改良に力を注ぎ、様々な試みをなし、その水稲技術を近郷の農村に広めていったとされています。これらの技術より、この地域の酒が確立されていったことが伺えます。
大正11年(1922年)には、互助精神の醸成と醸造技術研鑽を目的とした「耶麻醸友会(現 五味会)」が設立され、長年伝わる醸造法に加えて品質の向上を図るべく、当時一大生産地であった兵庫 灘の醸造法を取り入れながら、それぞれの酒蔵が自己研鑽を行いました。現在では「喜多方杜氏組合」が、この地域の酒質の向上を図っています。
さらに、この地域における永続性ある酒造業、産地米の安定的な生産の実現、発展を目的として、平成7年(1995年)から喜多方の生産者グループと協力し減農薬・減化学肥料栽培による酒米育成に取り組んでおり、喜多方のテロワールを今後語り続ける上で欠かせない環境の整備を図っています。
原料及び製法
米及び米こうじには、産地の範囲内で収穫した3等以上に格付けされた米のみを用い、水は産地の範囲内で採水した水のみを用い、特定名称酒の製法品質要件にて製造し、産地の範囲内において貯蔵、容器詰めしたものであること。
管理機関
管理機関の名称:GI喜多方清酒管理協議会
住所:福島県喜多方市字北町2932番地(夢心酒造株式会社内)
電話番号:0241-23-0400
地理的表示「喜多方」を使用するためには、これを使用する清酒の製造場から出荷するまでに、各規定について管理機関が作成する業務実施要領に基づいて確認を受けなければなりません。
(Text : 山路 日出夫)
この記事の筆者

日本ツーリズム運営局(オフィスイチヤマ)
日本ツーリズムは日本酒に対する潜在的な需要を発掘すると共に、日本各地の蔵元さんとユーザーをつなぎ、日本酒で地方を元気に、そして日本を元気にして行くと共に、世界へ日本酒の魅力を発信していくことを目指して行きます。
office-ichiyama.com